ドラム教本 廃刊のお知らせ(ビギナーのためのドラム教室)
ジャズドラム教室のタイトルで初刊から30余年、中・高校における吹奏楽団備品や個人練習用にご愛用頂き有り難うございました。
現在はまさにPC打ち込みの時代、ドラムも演奏から視覚的要素重視のスポーツ的な要素に変化しています。
音色や音符の打ち分け、拍子、フレーズなどを重視した、楽器演奏用としての本来のアナログ的な教則本はひと昔前の古い産物となってしまいました。
これらを考え、私から出版社に出向き絶版を申し出、合意に至りましたのでご報告申し上げます。

1、基本編(シングルストローク中心)
スティックの持ち方、構え方から四分音符、八分音符と徐々に細かい(速い)音符へと順を追って練習できます。
シングルストロークで演奏可能なリズムパターン(エイト、十六ビート、ボサノバ、ラテンリズム、他)の楽譜が多く載せられており、吹奏楽やクラシックドラムを勉強している人たちに好評です。2、応用編(ダブルストローク中心) フィンガーコントロール
フラム、ラフ、パラディドル、レッスン25、ラタマキュー、5つ打ち、9つ打ち、ロール奏法、ラテン(ダンス)リズムのパターンなど
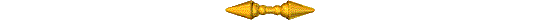
やさしい打楽器教本 小物打楽器教本
カラオケボックスに置いてあるタンバリンやマラカスを手に、歌い手の伴奏をした経験はありませんか。
簡易楽器なので手に取れば誰にでも音は出せますが、雑音だけに楽器として取り扱うのは難しいです。
伴奏の積りが邪魔だなんてお叱りを受けた経験があるかも知れません。
幼稚園などではリス組集合なんてタンバリンをパンパンと叩いている光景を目にします。
本来は合図用なので使い方としては間違いではありませんが、最低限の小物楽器としての知識は頭に入れておく必要が有るのでは、と考えます。
幼稚園や音楽教室の先生方へ
最近の童謡はマンボやチャチャチャ、サンバなど軽快なリズムの曲が多くなりました。
これらのラテンリズムの小物楽器使用例を、リズム別にパターンとして一覧表示しています。
ピアノ伴奏のみならず、小物打楽器を加えてみてはいかがでしょうか。
唱歌の場合でもオリジナルのピアノ伴奏ではなく、マンボなどのリズムなどに替えて演奏すると雰囲気が変わります。 発表会では特に盛り上がるのではないでしょうか。
著者(猪瀬雅治)による小物打楽器の叩き方講習会も簡易打楽器の新しい発見としていかがでしょうか。

楽器店での購入orネット販売をご利用下さい
多い質問
ドラム教室卒業について
宮地楽器神田センターでのドラム教室は卒業させて頂きました。最近のデジタル音楽の台頭で、ドラマーはスポーツ感覚で手足をバタつかせ、髪を振り乱しての一見熱演が受けているからです。素晴らしい事ではありますが、楽器として扱っていただけていないのがちょっぴり残念に思います。長年の経験から習得する事ができた音色や拍子、ノリなどを後輩に伝えたい気持ちはありますが、これも時代の流れかと思います。
私のレッスンでは拍子(グルーヴ感)など、打楽器プレーヤとしての役割を音楽の基本から習得し、息の長いプレーヤー育成をめざしました。 2枚皮の裏皮まで抜けた音色の追求に関しては特に気を使い、本物の太鼓の音を目指したものです。その他、打面にゴリゴリとこすりつけるむらのあるロールではなく、フィンガーコントロールによるスティックの先端を十分に返したダイナミックなロール奏法の伝授です。ノリに関してはクラシック、ポップス、電子打ち込み音楽との相違点などを追求しました。
現在は本物を追求したい仲間が集まって和気あいあいで楽しんでおります。
ドラムスの練習方法などで疑問や質問などがありましたらメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
・リズムとは ・拍子(グルーヴ)とは ・クラシックとポピュラーのノリの違い ・ノリとは(前ノリとかジャストとか)
・ボサノバとドサノバの違い ・サンバとバーさんの違い ・パラディドルとプラモデル ・音の抜け 他